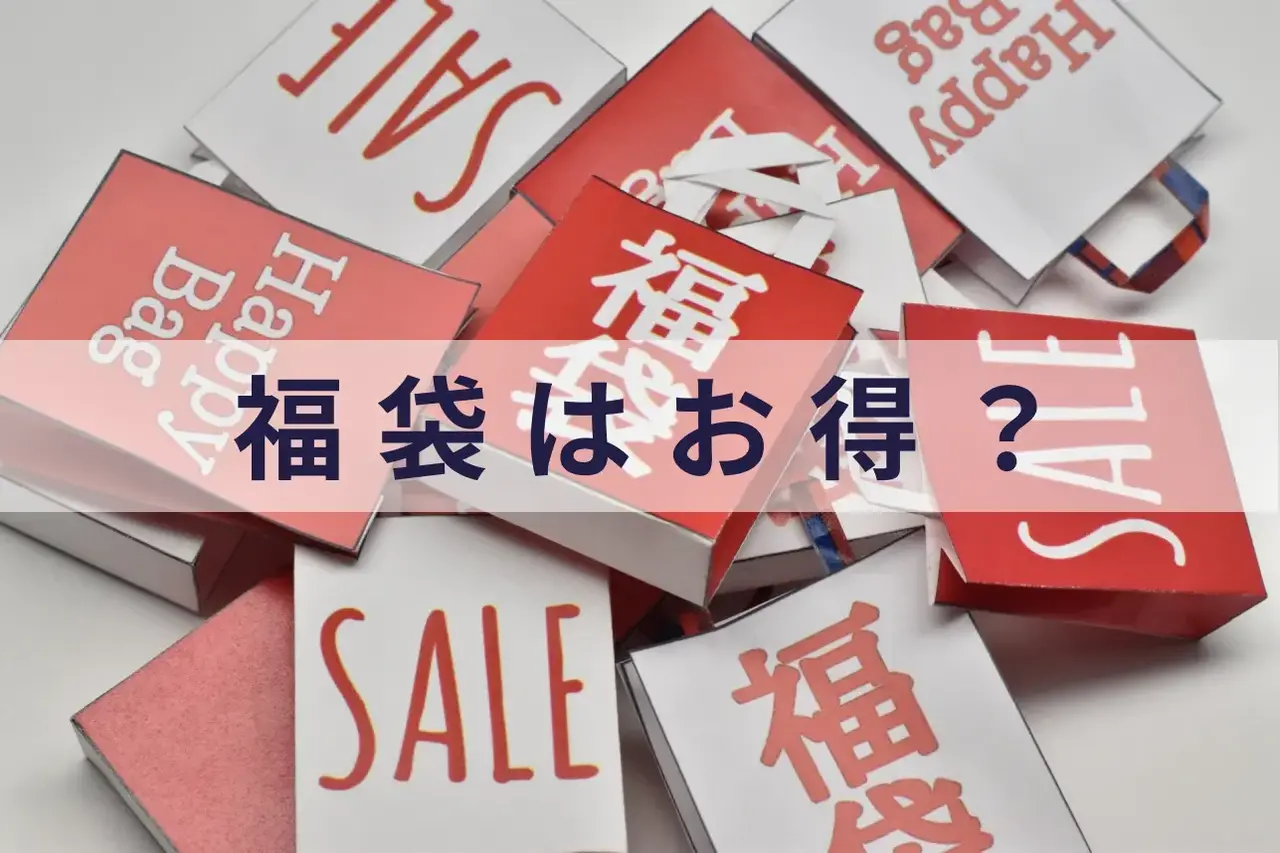諸説ありますが、起源は江戸時代に遡るようです。日本の独特な買い物文化を象徴する側面もある福袋について、心理的な背景から解説していきます。
福袋の魅力とは?心理調査から見る購買行動
なぜ福袋は毎年人気なのか?
少し古い論文になりますが、名古屋女子大学短期大学で行われた調査によると、多くの消費者が福袋に求めているのは「夢」と「お買い得感」であるそうです。
一般消費者の65.5%が「夢がある」からと回答し、学生は「お得」を最大の理由に挙げています。
不確実性の魅力、中身への期待感が購買意欲を掻き立てしくみは、ギャンブルと近い心理的な効果と言えるでしょう。
福袋購入者の満足度は1~2割程度
興味深いことに、調査によると福袋購入者のうち「100%満足」という回答は1~2割程度。つまり、8~9割の人が完全な満足には至っていません。
それでも、多くの人が次年度の購入意欲は高いままになっています。
ご自身の体験でも「期待して買ってみたけどいまいちだった」「けどなぜか毎年買ってしまう」という経験があるのではないでしょうか?
福袋に対する期待感

福袋の購入体験として、完全な満足ではなくても、ある程度の満足が得られれば再購入につながる傾向があります。
実際の商品価値(新発売時の価格の2~3倍相当が入っている)が評価されているのかも知れません。
そして中身が分からないからこその「予想外の喜び」と「わくわく感」。
それ以外の、福袋の魅力は何でしょうか?
お正月の福袋セールに潜む心理
お正月セール福袋の心理的魅力

正月に関していえば、新年の「縁起物」という文化的価値や、「初売り」という特別感もプラスに働いているでしょう。
人々の気分が祝祭的で、通常より冒険的な購買行動を取りやすいですし、学生であればお年玉などで購買意欲が高まる時期でもあります。
福袋が毎年注目される理由とは
そういった時期ですので、あらゆるお店や企業が福袋を販売することが恒例になっています。
販売する側としても、企業の決算期に12月末が多く(※)、またブラックフライデーや年末セールに売れ残った商品をセット販売する、という慣習が残っています。
型落ちモデルを格安に欲しい消費者と、在庫を処分したい企業の利害が一致しているイベントと言えるでしょう。
(※東証プライム上場企業 社数構成比で13%と、3月の68%についで多い)
原価の高い商品とリセールバリュー
正月という「ハレの日」に販売することの心理的効果に加え、福袋購入の理由のひとつである「本来高値だった商品が安値で手に入る」というメリット。
さらに、近年の傾向として、メルカリなどを筆頭に CtoC で気軽に販売できるようになった事も挙げられます。
リセールバリューが高いブランド品や、希少価値の高い商品などが人気なのは、福袋の「お得」という側面、資産的価値があるという安心感に結びつくからではないでしょうか。
福袋購入で失敗しないためのポイント
なぜ福袋がこんなにも人を引き付けるのか?
福袋の魅力について心理学的な分析も含めて見てきましたが、ここからは消費者として注意したほうがよいポイントについて、解説していきたいと思います。
人気ブランドやお得度だけで判断しない
福袋の定番商品といえば、ファッション(アパレル)ブランド。
洋服などは顕著ですが、原価や新品価格(定価)が高いからといって、その人に似合うかどうか、必要かどうかは別問題です。
いわゆる当たりの商品が(もしくは他の封入商品が)欲しいものかどうかを吟味しましょう。
アパレルにしても電化製品にしても、最新のデザインや機能を期待しすぎない事も重要です。
「人気」や情報に惑わされない
先の調査で回答された福袋の購入理由である「皆が買っている」「情報に惑わされる」という傾向には、注意しましょう。
とくに学生に多い傾向にありましたが、お祭りムードや回りの意見に惑わされ購入してしまうというケースです。
SNSなどでの接触率が高い商品は、マーケティングによって演出されている可能性が高いです。
自分本当に必要な商品か、よく考える時間を設けたほうが良いかも知れません。
福袋を作成、販売する人の視点
福袋は「買う」だけでなく、「作る」人がいます。
これだけ社会に浸透していると、多くの人は消費者でもあるかも知れませんが、ショップの店長や責任者といった人達は「福袋を詰め合わせる」という仕事をされたことがあるかも知れません。
福袋の中身や価格設定
福袋の中身について、先の論文では「新発売時価格の2~3倍相当の価値提供が基準」として示唆されています。
時代背景や、ジャンルや原価率の高い低いなどで違いはあると思いますが、概ね妥当な印象があります。
また、福袋の醍醐味を味わってもらうために、実用的なアイテムと遊び心のあるアイテムをミックス(定番商品だけでなくサプライズ要素)するのもオススメです。
楽しさと「希少性の原理」を活用
いくら継続率(毎年)が高いとはいえ、完全にがっかりさせてしまっては元も子もありません。
売れ残りなど在庫処分品のみの詰め合わせは避け、ハズレでも楽しめるような購入体験を提供できるように工夫すると良いでしょう。
また、心理学的には「希少性の原理」の活用ができます。手に入りづらい商品を封入することで、購買意欲が刺激されます。(ただし、いわゆる抱き合わせ販売にならないように注意が必要です)
数量限定による価値向上も効果的です。
また、正月でなくとも、販売タイミングも「その時期ならでは」の意味づけを考えましょう。
社会的証明やブランドを活用
先ほどは、惑わされないよう注意という話をしましたが、販売者の立場では「みんなが買っている」という印象づけは重要になってきます。
他者の購買行動の影響(特に若年層)は大きく、口コミやSNSでの拡散効果も狙えます。
同様に、ブランドマーク入り商品は評価が高い傾向がありますので、可能であれば有名ブランドを取り扱うとよいでしょう。
ブランド価値の毀損リスクへの配慮しましょう。(品質管理の徹底、極端な安値での販売は避けるなど)
コミットメントと一貫性
調査によると、満足度80%以上は次年度購入意向が高い傾向にありました。
心理的なテクニックも、「顧客満足度を上げる」という視点で活用してみましょう。
福袋は単なる商品販売ではなく、購入体験全体をデザインする必要があります。顧客の期待と現実のバランスを取りながら、継続的な購買につながる満足度を提供することが重要です。
福袋のトレンド
最新ニュースから探る人気福袋の傾向
ブランド商品や家電製品など定番のジャンルでは、新年の福袋の販売予約が、年内11月に完売してしまうなどの人気を博しています。
 引用元:starbucks.co.jp
引用元:starbucks.co.jp
例えばスターバックスの福袋では、店頭では購入できない限定商品(希少性の原理)を軸に、コーヒーといった定番商品が封入されたバランスの良い顧客満足度の高い福袋になっています。
ガチャやオンライン福袋
最近では、ポケカを筆頭としたトレーディングカードゲームの人気を背景として、福袋や、それをオンラインで再現した「オリパ」も盛んなようです。
オリパとは「オリジナルパック」の略で、ネットや店舗で買えるトレーディングカードのセット賞品です。店舗によって内容やコンセプトが異なります。
引用元:オリパ.com
オリパでは、当たりカードは公開されているケースがほとんどのようです。
トレカは中古のマーケットが発達しており、当たりを引ければ普通にショップで買うより「お買い得」であったり、そもそも入手しづらいカードが封入されており(希少性の原理)、人気を博しています。
その他、ユニークな福袋のご紹介
▼フード・飲食店系
・らーめん(複数店舗の名店ラーメンセット、人気店のらーめんと什器のセット)
・お酒(ワイングラスなどの食器とセット)
▼体験・観光系
・占い館の福袋(複数種類の占いチケット、パワーストーンや開運グッズ付き)
・道の駅福袋(その地域の特産品を、産地直送の福袋として提供)
▼ホビー・エンターテイメント系
・ボードゲーム福袋(複数のゲームをテーマ別にセット)
賢く活用する
福袋は、消費者にとっては普段の買い物では得られない体験を得られる機会になり、ショップや企業にとってはまたとない販売機会と言えるでしょう。
どちらの立場でも賢く、福袋を活用してみてくださいね。
–
参考:福袋に関する研究ー消費者としての評価ー 加藤恵子
jstage.jst.go.jp