今日、MBTIツールは世界で最も広く利用され、認知されている性格ツールであり、年間約200万人が診断を受けていると言われています。
MBTIの歴史と心理学的根拠(診断方法やタイプ別相性含む)、そして日本の文化的背景の中でMBTIの流行と影響について、焦点を当てて包括的に解説したいと思います。
MBTIの起源と歴史

MBTIは、キャサリン・クック・ブリッグス(1875–1968)とその娘イザベル・ブリッグス・マイヤーズ(1897–1980)によって開発されました。
ブリッグスは、スイスの精神科医カール・ユングが1921年に出版した著書『心理学的類型』に触発され、家族や友人への観察を通してそれを応用しました。
その後、彼女と娘は行動の違いを分類し、それらをユングの概念と結びつけ、その違いを分類するためのツールを開発します。
イザベル・マイヤーズはその後50年以上にわたりMBTIの開発を続けました 。その初期の利用は、医療現場、特に看護師間の協力関係を改善するために行われました 。
MBTIは、明確な実用的目標、すなわち対人関係の理解と改善を目的に考案され、そのことが、様々な応用分野での早期採用に貢献したと考えられます。
現在のMBTIが適職診断などにも用いられるのも、こういった歴史を踏まえると興味深いポイントです。
MBTIの構造:基本的な概念と方法論
MBTI診断は4つの二分法からなり、これらの二分法は、それぞれが独立した選好として設計されています。
4つの二分法
MBTIは、個人の性格を理解するための基盤として、以下の4つの独立した二分法を特定しています。
● 内向型(I) – 外向型(E)
エネルギーの方向性(内面的世界か外的世界か)と、どのようにエネルギーを得るかに焦点を当てます。内向型の人は、内なる思考やアイデアにエネルギーを向け、一人で過ごすことでエネルギーを充電する傾向があります。一方、外向型の人は、人々や活動との交流からエネルギーを引き出し、外の世界に注意を向けることを好みます。
● 感覚型(S) – 直観型(N)
情報の収集と処理の方法の違いを示します。感覚型の人は、五感を通して得られる具体的で現実的な情報を好み、事実や詳細に焦点を当てます。一方、直観型の人は、パターン、可能性、そして物事の背後にある意味合いに関心を持ち、抽象的で理論的な情報を重視します。
● 思考型(T) – 感情型(F)
判断や意思決定の基準の違いを表します。思考型の人は、論理的で客観的な分析に基づいて意思決定を行い、公平性と一貫性を重視します。感情型の人は、個人的な価値観や他者への共感に基づいて意思決定を行い、調和と人間関係を重視します。
● 判断型(J) – 知覚型(P)
外界への接し方やライフスタイルの好みの違いを示します。判断型の人は、計画的で組織化された生活を好み、秩序と構造を重視し、物事を決着させることを好みます。一方、知覚型の人は、柔軟で自発的なアプローチを好み、選択肢を開いたままにして、状況に応じて適応することを楽しみます。
16の性格タイプ
これらの4つの二分法の組み合わせにより、16の異なる性格タイプが生まれます。各タイプは、4つの文字のコードで表され、それぞれの二分法における好みを反映しています。
例えば、ISTJ(内向-感覚-思考-判断)やENFP(外向-直観-感情-知覚)などがあります。これらの16のタイプは、アナリスト(分析家)、外交官、番人、探検家といったより広範なグループに分類されることもあります。
MBTIでは、このすべての16タイプを等しく有効で健全であると見なし、性格の肯定的な見方を提供することを目指しています 。
MBTI診断の結果の解釈が、ポジティブなフィードバックの提供であること、そしてこの明確で理解しやすい性格分類が、MBTIの人気に貢献しているといえるでしょう。
診断プロセス
MBTIは、自己報告式の質問票として実施されます 。
通常、一連の二者択一式の質問が含まれており、個人は自分の好みを最もよく表す2つのオプションから選択します 。Form Mなどの形式では、約15〜25分の所要時間で、時間制限はありません 。
Step IとStep IIを含む様々な形式があり、質問項目数も異なります 。Step IIでは、各二分法内の側面をより深く掘り下げます 。
詳しくは後述しますが、この二者択一形式は、個人が両方のオプションに共感したり、スペクトルの途中に位置したりする可能性を表現できないため、専門家からは批判の対象となっています。
対人関係のダイナミクス:MBTIタイプ間の相性の探求
MBTIは、特に人間関係において、異なる性格タイプ間の相性を探るためによく使用されます。
特定のタイプがより「似た仲間」であるとか、「挑戦的な反対者」であるといった使われ方も多く見られます。
| 相性が良いとされる組み合わせ |
|---|
| ENTP(討論者型)とISFP(冒険家型) |
| ESFJ(領事館型)とINTJ(建築家型) |
| INTP(論理学者)とESFP(エンターテイナー) |
| ISFJ(擁護者型)とENTJ(指揮官型) |
| ISTP(巨匠型)とENFP(運動家型) |
| INFJ(提唱者型)とESTJ(幹部型) |
| ESTP(起業家型)とINFP(仲介者型) |
| ENFJ(主人公型)とISTJ(管理者型) |
ただし、人間関係の相性はMBTIタイプのみによって予測されたり決定されたりするものではなく、例えばコミュニケーション、共有された価値観、相互尊重などが重要な要素であることは、常に意識しておく必要があります。
「性格診断」に基づく相性の考え方、単純化はときに魅力的ですが、人間関係の成功をMBTIタイプに還元することは、人間関係の複雑さや各タイプ内の個人の違いを無視してしまうリスクが伴います。
MBTIの相性に過度に依存すると、潜在的なパートナーに対する早まった判断や、既存の関係における不必要な懸念(疑心暗鬼)につながる可能性があるので、十分に注意しましょう。
MBTIの科学的根拠
科学的妥当性については批判が多い
MBTIの開発組織であるマイヤーズ・ブリッグス社は、この指標の信頼性と妥当性は数百もの個別の研究で確立されていると主張しています。(※1)
しかし、科学界からは、その科学的妥当性と信頼性の欠如に関して重大な批判も寄せられています。(※2)
研究によると、再検査の信頼性は低く、短期間でさえかなりの割合の個人が異なるタイプに分類されているとのことです。(※3)
(※1)https://ap.themyersbriggs.com/content/Quick_Tips/MBTI_FAQ.pdf
(※2)https://humanperformance.ie/myers-briggs-type-indicator-pseudoscience/
(※3)https://www.psychologytoday.com/us/basics/myers-briggs
また、MBTIタイプは、仕事の業績やキャリアの成功といった重要な人生の成果を一貫して予測するわけではないという研究もあります。
MBTIの妥当性と信頼性を裏付ける科学的証拠は弱いものであり、多くの研究者は、その方法論的限界のために、MBTIを疑似科学と見なしています。
心理学的な根拠はユングの類型論
MBTIの理論的根拠は、カール・ユングの著作にありますが、ユングの類型論は、実証的研究ではなく、臨床観察に基づいた理論モデルであったことに留意する必要があります。
MBTIは、離散的で二分法的な性格タイプという仮定に基づいています。しかし、今日の心理学においては、性格特性は絶対的なカテゴリーとしてではなく、連続体(スペクトラム)として存在しているという説が支持されています。
タイプが真に離散的である場合に予想される、好みのスコアの二峰性分布を裏付ける経験的証拠はないという批判は、説得力のあるものでしょう。
ビッグファイブとの相関はある
一部の研究者は、MBTIをビッグファイブモデル(FFM。五因子モデル)の観点から再解釈しようと試み、MBTIの尺度との一部の側面との間に相関関係があることを発見しました。
ビッグファイブは、理論モデルとして堅牢で、近年の心理学界においてより広く受け入れられている性格モデルです。
ビッグファイブとの相関関係は、MBTIがいくつかの広範な性格傾向を(あくまで結果的にではあるけれど)捉えている可能性を示唆しています。
MBTI診断が一定の説得力や納得感を持って受け入れられたのは、そういった側面が一因かも知れません。
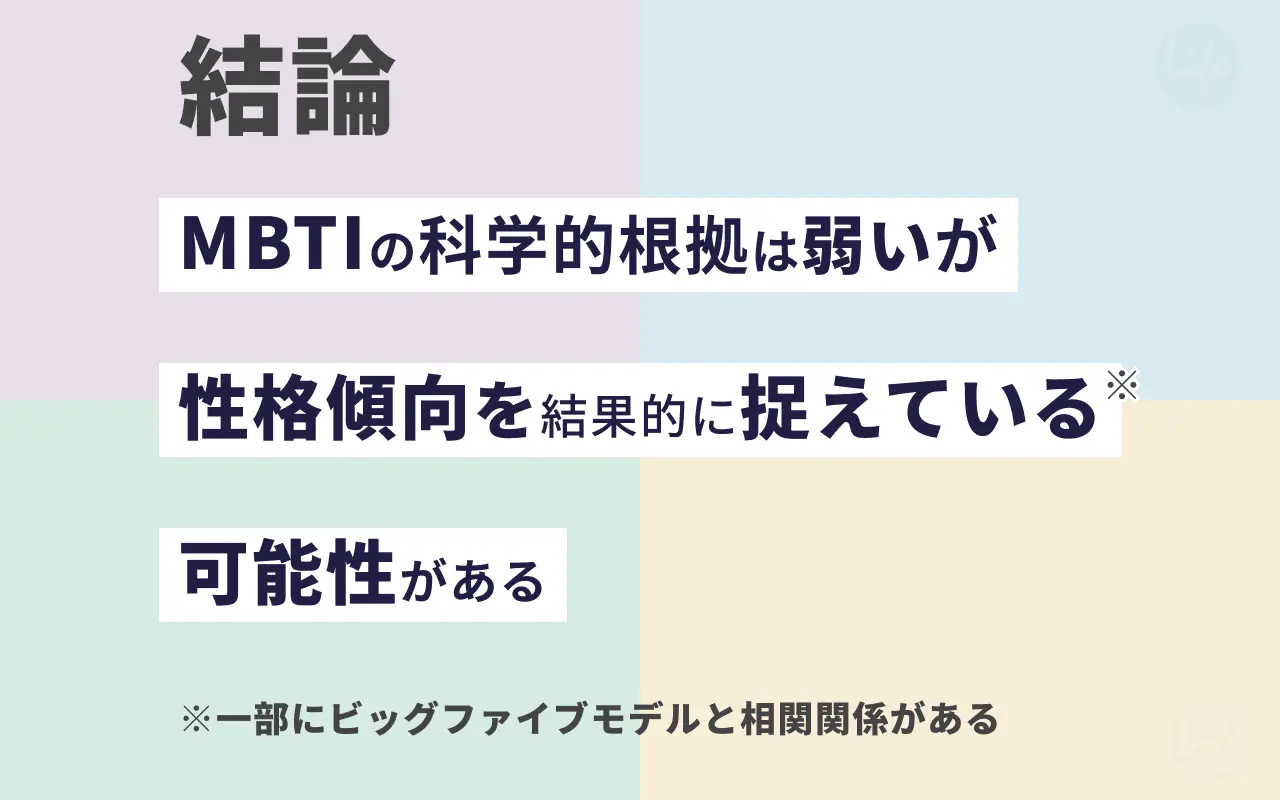
しかし、MBTIの性格タイプへのカテゴリー別のアプローチは、性格心理学における一般的な理解、すなわち特性は連続体(スペクトラム)であるという理解とは根本的に異なっていることには注意が必要です。
| 研究著者 | 出版年 | 主な発見(信頼性、妥当性 etc.) |
|---|---|---|
| Carskadon | 1977 | MBTIの信頼性(一貫性)は、特に時間の経過とともにテストを再受験した場合に問題がある可能性があることを示唆 |
| McCrae & Costa | 1989 | MBTIはユングの理論を適切に反映しておらず、心理測定特性が不十分であり、専門的な心理学的目的には推奨されない |
| Pittenger | 1993 | MBTIには深刻な心理測定的問題がある(低い妥当性と信頼性、不自然な二分法)。研究と実践における使用を推奨しない |
| Boyle | 1995 | MBTIの因子構造はユングの理論と一致しておらず、信頼性と妥当性の問題がある |
| Furnham | 1996 | MBTIは人気があるが、その心理測定的妥当性は広く批判されている。因子構造は16の独立した因子を支持していない |
| Capraro & Capraro | 2002 | 多くの研究でMBTIの信頼性と妥当性が低いことが示されている |
| Salter et al. | 2023 | MBTIの支持者は、その信頼性と妥当性を示すエビデンスを提示している |
日本におけるMBTIの歩み
日本に初めてMBTIが導入されたのは1968年という説がありますが、定かではありません。
一般的に知られるようになったのは、1982年に大沢武志によってMBTI診断の質問票が翻訳・出版された以降であると推察されます。
参考(Amazon書籍):「人間のタイプと適性: 天賦の才 異なればこそ」
近年では、SNSやインターネットを通じて、自己理解や他者理解のツールとして、特に若年層の間で人気が高まりました。
日本社会におけるMBTIの受容は、集団主義的な文化の中で個人の特性を理解し、他者との調和的な関係を築きたいというニーズと合致していると考えられます。
また、自己分析や自己啓発に対する関心の高さも、MBTIの普及を後押しとなり、自己理解やチームワーク向上のためのツールとしての側面も担うようになりました。
MBTIが日本で広く受け入れられた理由は、文化的背景(例えば調和を重視する傾向や自己分析への関心)と関連している可能性があります。
また、日本独自の現象として、MBTIの性格タイプを擬人化したり、アニメやゲームのキャラクターに当てはめて議論したりする文化が、特にオンラインコミュニティを中心に形成されました。
このような現象は、MBTIが単なる性格診断ツールとしてだけでなく、コミュニケーションの共通言語やエンターテイメントの要素としても受け入れられていることを示唆しています。
まとめ:MBTIの未来
MBTIは、その歴史、構造、評価方法において、自己理解と対人関係の議論のための人気のあるツールであり続けています。
日本におけるMBTIの流行は、個性を尊重し、多様な他者との関係性を円滑に築きたいという社会的なニーズを反映していると考えられます。
しかし、その科学的妥当性と信頼性に関しては、十分な根拠があるとは言えません。
そのため、MBTIの結果は絶対的なものではなく、自己理解の一助として活用する際には、その限界を理解しておくことが重要です。
今後、MBTIがどのように受け止められていくのか、もしくはより科学的な性格モデルに移行していくのか、その動向を注視していく必要があるでしょう。
<参考文献>
1. Carskadon, T. G. (1977). Stability of MBTI types. Research in Psychological Type, 1(1), 23-30.
2. McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1989). Reinterpreting the Myers-Briggs Type Indicator from the perspective of the five-factor model of personality. Journal of Personality, 57(1), 17-40.
3. Pittenger, D. J. (1993). The utility of the Myers-Briggs Type Indicator. Review of Educational Research, 63(4), 467-488.
4. Boyle, G. J. (1995). Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Some psychometric limitations. Australian Psychologist, 30(1), 71-74.
5. Furnham, A. (1996). The Myers-Briggs Type Indicator: A critical review and bibliography for research and practice. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 122(3), 337-367.
6. Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2002). Myers-Briggs Type Indicator validity issues. Research in the Schools, 9(1), 1-6.
7. Salter, D., журнал «The Psychologist». (2023). Дебаты по MBTI. Получено с
8. The Myers-Briggs Company. (n.d.). Technical Information. Retrieved from
